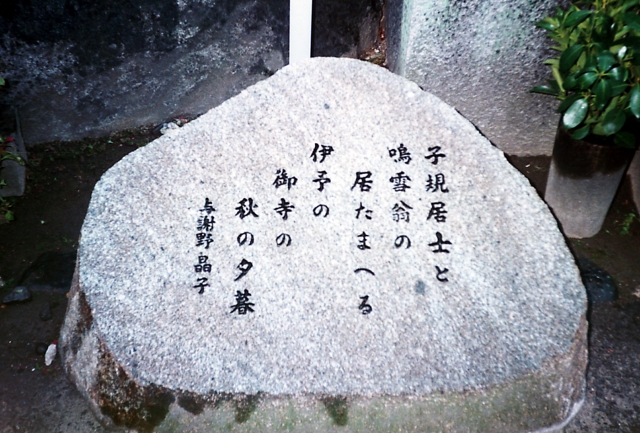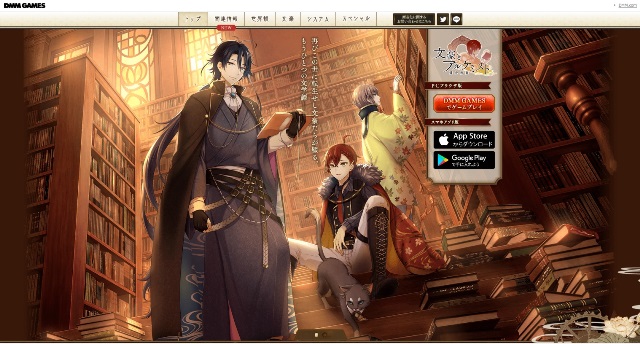記事一覧
-

良い短歌には生きるヒントがある 短歌入門書は人生哲学書でもあった
『はじめての短歌』という本をご存知だろうか。この本は、歌人である穂村弘が、「良い短歌を詠むにはどのような考え方や言葉選びをすればよいのか」をわかりやすく説明... -

イケメン、美女、少年…キャラクター化された文豪たち なぜその姿なのか?を徹底考察
サブカルチャー大国である日本では、どんなものもキャラクターになる。競走馬、偉人、刀剣、細胞、国……。そうしたモノに我々が抱くイメージを抽出し、親しみやすい形を... -

青鯖の缶詰風ポーチ、名作がモチーフのお茶…ユニークな文学グッズが話題のフェリシモ「ミュージアム部™」に話を聞いたら、文学愛がすごかった
何気なくSNSを見ていたある日、衝撃的なものを見つけました。その名も「文学作品イメージティー」。中島敦『山月記』、高村光太郎『智恵子抄』、室生犀星『蜜のあわれ』... -

『ゴールデンカムイ』とアイヌ文化から学ぶ、社会や自己との上手な向き合い方
テレビやS N Sでは多様性や生きづらさが叫ばれ、書店には社会や自己との向き合い方、自己肯定感の高め方について取り扱った本が並んでいる。そんな生きづらい現代をより... -

【エピソード6】壁一面に本棚のあるゲストハウス 旅人たちそれぞれの物語
子供の頃から、旅に出るときは本を一冊カバンに忍ばせていた。旅と本はいつもセットだ。25歳になった私は、思い立って仕事を辞めて、壁一面の本棚があるゲストハウスで... -

原作と映画どっちがお好き?映画化された名作小説4編を紹介(アメリカ・イギリス文学編)
みなさん、映画と小説、どっちが好きですか? きっと「どっちかだけなんて選べない!」という方も多いはず。そんなみなさんのために、今回はアメリカ・イギリスの文学作... -

美女に恋した男たちの争い、労働者が資本家に復讐…宮沢賢治のあまり知られていない作品と素顔を紹介
宮沢賢治といえばどんなイメージがあるだろうか。有名作品では『銀河鉄道の夜』や『注文の多い料理店』、『よだかの星』などが挙げられ、幻想的かつ透明感のある情景描... -

雲、汗、サイダー、ラムネ…同じ言葉でも、短歌にしたら解釈も景色も十人十色だった
枯葉、落ち葉、かれっぱ……詩人・金子みすずは、1つのできごとをいろいろな言葉に置き換えて遊んでいたらしい。日本語の特徴として、ある物事がさまざまに言い換えられ... -

韓国・ソウル旅行に行ってみた!グルメ、エステ、ショッピング三昧の2泊3日を紹介
韓国・ソウルに2泊3日の旅行に行ってきた。大学生になったら海外旅行をしたい! と思いながら受験勉強に勤しんでいたものの、入学後に待っていたのは新型コロナウイル... -

太宰治、石川啄木、永井荷風…文豪たちもメロメロになった芸者遊びの魅力
借金、薬物、女遊び……。明治、昭和の文豪たちは、小説だけでなく暮らしぶりに注目されることが多く、エピソードに事欠きません。この記事では、文豪たちのかずかずの逸...